AIが上手に整えてくれる!しかし、過信は禁物!! [代表:宮谷]
昨日、今後展開予定の新サービスの広告文面をまとめるため、一通り要件を書き出しました(これをRDD:Requirements Definition Documentといいます)。

その後、AI(ChatGPT5を利用)に投げかけて添削してもらい、さらに自分で細かく修正…という作業を繰り返しました。

結果、2日かかると思っていた仕事が、なんと2時間ほどで終了!
「もっと早くこの時間を確保すればよかった」と反省しました。
昔なら、上司や詳しい人に添削をお願いして「添削前より悪くなる」なんてこともありました(笑)。

しかしAIの添削は違います。多少「これは違うかな」という部分があるにせよ、概ね「素晴らしくアップデート」された文章を返してくれます。
つまり、短時間で成果を大きく改善できるのです。

今や多くの職場でAIが使われ始めています。逆に使わなければ「単に仕事が遅い人・職場」と見なされかねません。
ただし、この風潮が行き過ぎることには危惧もあります。
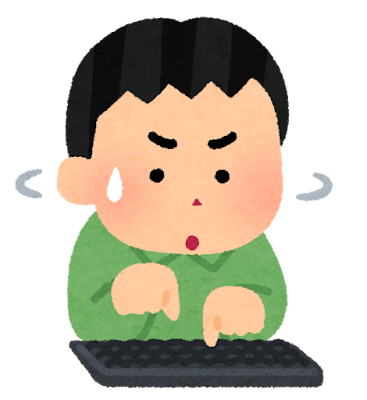
例えば、文章作成やプログラミング・計算は速くなっても、野菜や果物の生育は10倍にはできません。確認に時間がかかる仕事も多いはずです。

知人の産地直送農家さんも「まだ今年は梨を送ってこないのか!」というクレームが増えて困っているそうです。

「天候に左右されるので、もう少しお待ちください」と返しても「ネットには順調と書いてあった!」と更に言われてしまうとか…。
地域や畑ごとに生育状況は違うのに、ネット情報をうのみにされると説明は難しいですよね。

最近はGoogle検索でも、AIが作った要約が一番上に表示されることが増えました。便利ですが、間違いも多いので要注意です。
やはり情報をきちんと精査し、違和感があれば自分で調べることが必要です。
子どもたちにも、AI時代に必要な「情報を見極める力」をぜひ身につけてほしいと思います。
…とはいえ、我が家の息子も最近「ネットで見たけど…」という発言が増えており、間違った情報に振り回される姿を見て頭を抱えているところです(笑)。




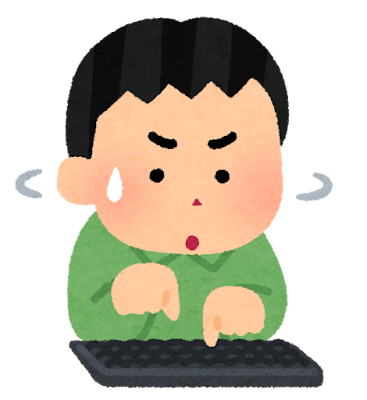


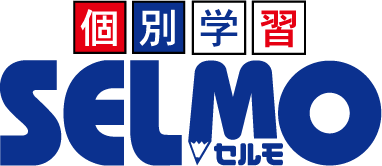



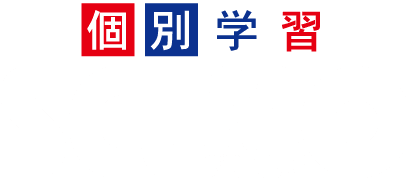 トップページへ戻る
トップページへ戻る
