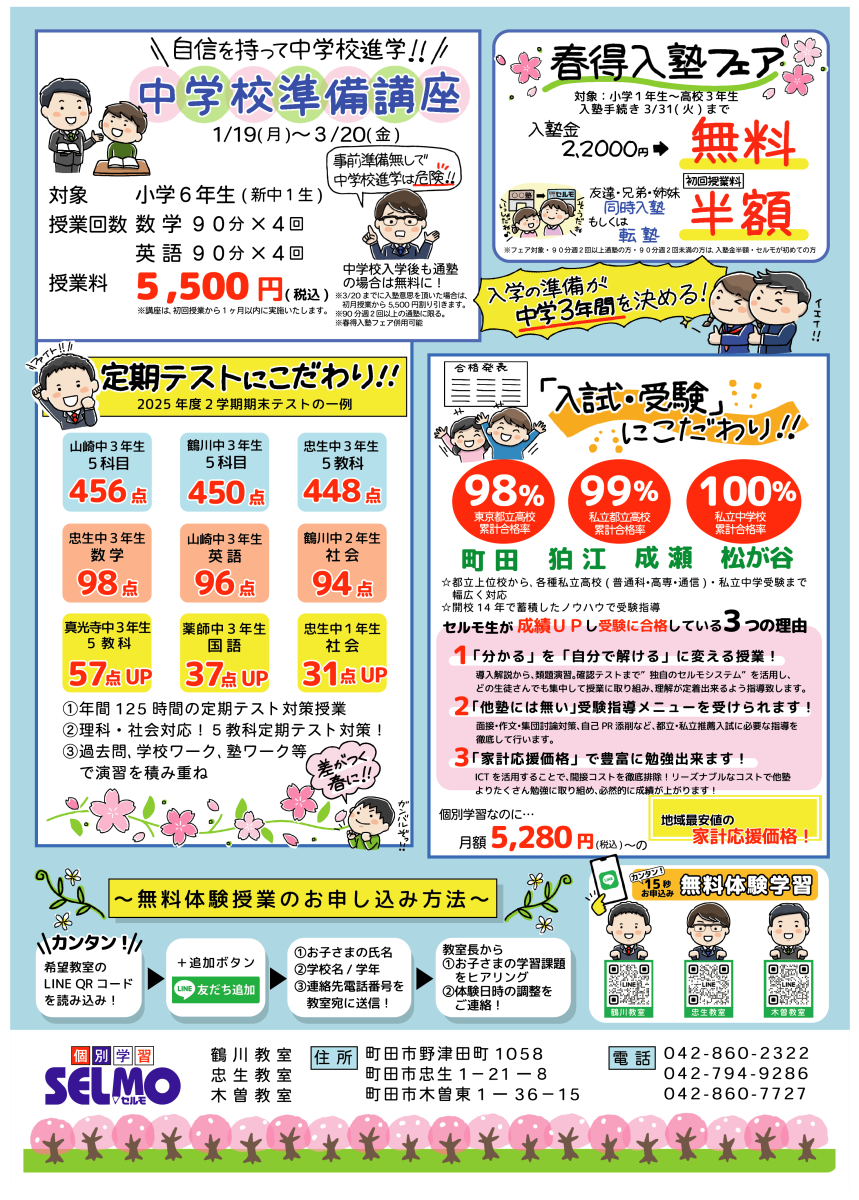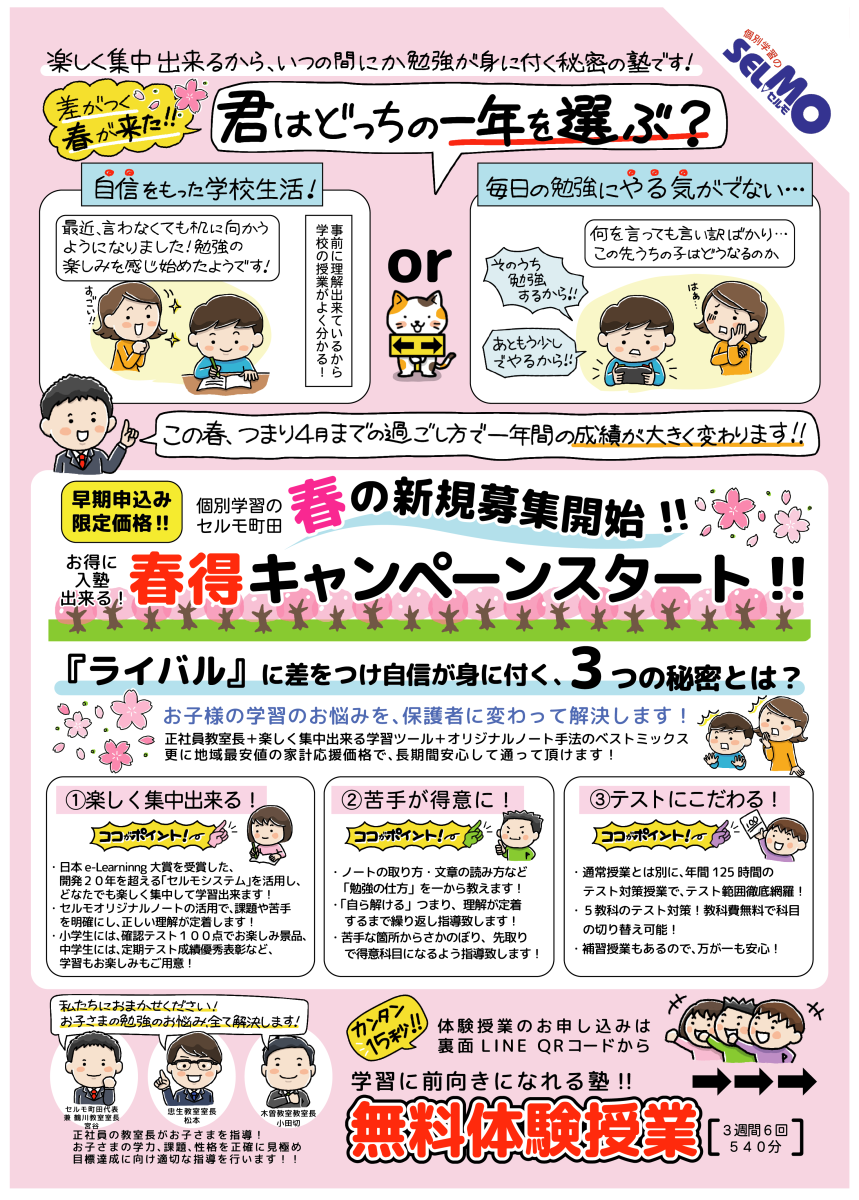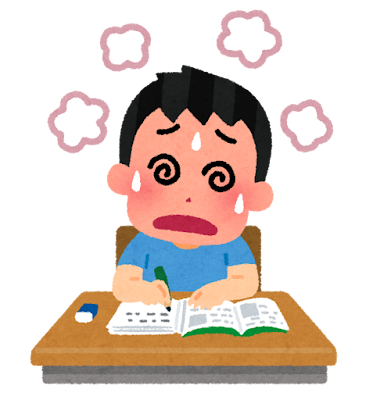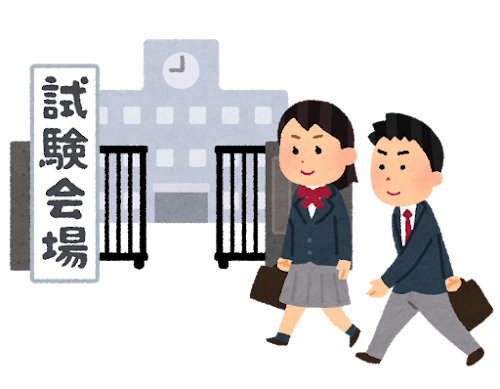「勉強がわかるようになりたい」「成績を上げたい」 そのためには、知識や経験といった「学力」そのものが必要ですが、実はそれ以前に大切な要素がいくつかあります。

長年多くの生徒を指導してきた中で、私が特に痛感しているのが次の3点です。
正しい着座姿勢
鉛筆の持ち方
ノートの書き方
これらは一見、学習内容とは無関係に思えるかもしれません。
しかし、これこそが「伸びる子」の共通点なのです。
① 集中力を支える「姿勢と呼吸」
姿勢の良し悪しは、**理解の「速さ」と「深さ」**に直結します。
姿勢が崩れると、肺が圧迫されて酸素の摂取量が減り、脳へ送られる酸素が不足してしまうからです。

中学2年生の理科で「呼吸とエネルギー」について学びますが、人間は酸素があって初めて心身をフル活動させることができます。

成績上位の生徒たちの共通点は、やはり「姿勢の美しさ」にあります。
もし、お子様が「口呼吸」になっていたり、鼻の通りが悪そうだったりする場合は、姿勢の悪さが重なるとより生活や勉強に影響が出ます。
鼻呼吸と口呼吸では、酸素量の違いはもちろんのこと、鼻腔での一酸化窒素の生成など血液の送られる栄養素に決定的な違いが出るそうです。
※ちなみに、私自身も鼻の通りが悪く、鼻の中の肥大した軟骨を除去する手術を受けて劇的に鼻の通りがよくなりました。

姿勢は幼少期からの習慣であり、ご家庭の声かけだけで改善するのは根気がいるものです。
最近は町田市内にも姿勢改善の専門家が多くいらっしゃいますので、プロの力を借りるのも一つの有効な手段です。
② 丁寧な思考を作る「筆記の習慣」
鉛筆の持ち方は、書く字の丁寧さに影響します。

高学年になってからの矯正は大変ですが、まずは**「ゆっくり書くこと」**から意識してみましょう。
また、筆記用具選びも大切です。
芯が太めで、余計な力を入れなくてもしっかり書けるものを選ぶと、書くことへのストレスが軽減されます。

本格的には、ペン字講座など書字を改善するための習い事もあります。
③ 「ノートは脳内の風景」である
成績の良い生徒のノートは、例外なく整っています。

私たちはよく**「ノートは脳の風景を写したもの」**とお伝えしています。
乱雑なノートという「風景」が脳に記憶されても、後から必要な知識を正確に引き出すことは困難です。

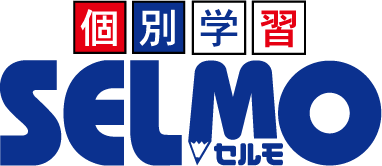



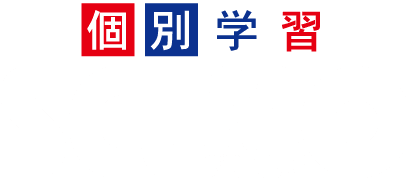 トップページへ戻る
トップページへ戻る