今朝ニュースを見ていると、先日ヘリコプター墜落事故で亡くなられたイランのライシ大統領の代わりを決める選挙が始まったとのことでした。

イラン大統領選挙 保守強硬派のほか改革派 穏健派からも立候補
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240604/k10014470131000.html
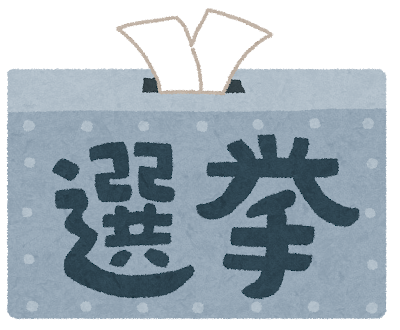
このニュースで興味深いのが、大統領立候補者の届け出が80人もいるということでした。

アメリカの大統領選挙でも立候補するのは数人なので、80人もいるんだ!と驚きました。

イランも意外と民主的なのかな?と思っていたら、ニュースの後半でイランの大統領はイスラム法学者などで作る「護憲評議会」による資格審査を経て正式に決まり、さらにこの護憲評議会は最高指導者のハメネイ師が選んでいるとのことでした。
前回の選挙では、改革派や穏健派の多くはここで失格となっているようで、色々な仕組みがあるのだな・・と分かりました。

このイランの大統領選挙の仕組みを受験生は知る必要はありませんが、実はアメリカの大統領選挙と日本の首相を決定する仕組みや制度の比較は、受験で出題されます。社会が試験科目にある東京都立受験生や神奈川県立受験生は、3年生で学ぶ公民の学習範囲なので把握しておく必要があります。
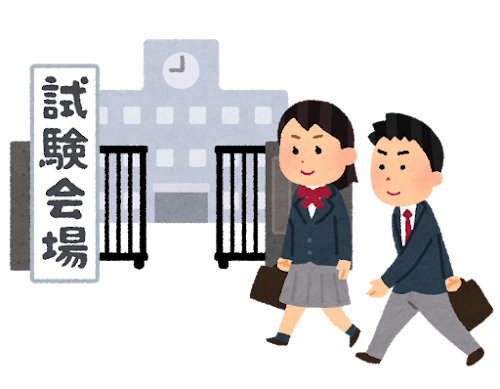
具体的な内容は、ここでは長くなるので割愛しますが、内容を知りたい人は下記のリンクからご覧下さい。
http://www.american-presidents.info/shushou.html
ところが、この公民の授業が曲者で、学校の授業時間数が足りないので、歴史の学習が毎年押してしまい、公民の学習をする時間が十分にありません。
学校の授業では公民の範囲の半分こなせれば良い・・くらいに思っておいたほうが良いです。中には、1/3くらいの進捗で受験が始まってしまう学校も・・。

つまり公民の範囲の大部分を自分で勉強するか、塾で補うしか無いのです。
しかし、公民は中学3年生のとって馴染の無い内容が多く、専門用語を理解・暗記するのが難しいです。それほどハイスピードで進めることが出来ません。

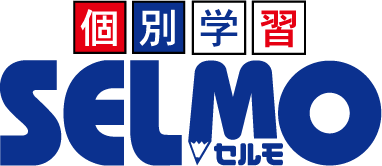



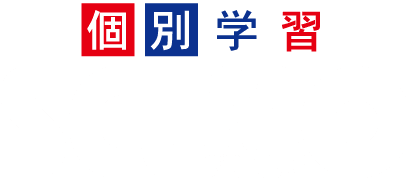 トップページへ戻る
トップページへ戻る